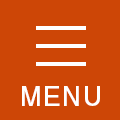教員情報詳細
- 氏名
- 小谷 民菜(KOTANI Tamina)
- 所属・職名
- 国際関係学部国際言語文化学科 准教授
国際関係学研究科 准教授(兼務)
- 部屋番号
- 一般教育棟2506号室
- Eメールアドレス
- kotani@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
1987年3月 三重大学人文学部文化学科卒業
1994年3月 東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学
1994年3月 東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学
学位
文学修士(東京都立大学・1990年)
専門分野
ドイツ文学
担当科目
ドイツ語Ⅲ、原典講読V(ドイツ語)、ドイツ語入門、演習、卒業研究、ヨーロッパ文化入門A(ヨーロッパ研究入門A:分担)、ヨーロッパ文化論Ⅰ(文学と社会)、ドイツ文化研究Ⅱ
主要研究テーマ
- ハインリヒ・ハイネの芸術評論
- 風刺画と文学との関係(19世紀前半フランス19世紀後半ドイツ)
- モニュメントの感性
所属学会
日本独文学会
日本感性工学会(評議員)
日本比較文化学会
日本感性工学会(評議員)
日本比較文化学会
主な経歴
1994年4月 静岡県立大学国際関係学部講師
2004年4月 静岡県立大学国際関係学部助教授
2007年4月 静岡県立大学国際関係学部准教授
2004年4月 静岡県立大学国際関係学部助教授
2007年4月 静岡県立大学国際関係学部准教授
受賞歴
2005年 日本感性工学会賞出版賞
主な社会活動
学習院大学人文科学研究所客員所員
教育・研究に対する考え方
現代の日本で「欧米」というとき、実はアメリカのことしか念頭に置かれていないことが少なくない。そして「外国語イコール英語」という単純な図式が大手を振って歩いている。英語の重要性は言うまでもないことだが、この言語ばかりを重視するあまり、偏った情報・知識、ひいては思想・世界観までもが日本の社会を覆ってしまうことを恐れる。ドイツ語の学習は英語・パソコン・専門の残りの余技ではなく、国際社会を見て生きていく上での代えがたい窓の一つになるといえる。そのレベルにまで学生たちのドイツ語の語学力を育て、ドイツ文化に触れる機会を提供していきたいと考えている。
芸術は、現状批判という混じりけのない言語を話すゆえに、独裁権力からは常に真っ先に攻撃・統制・抑圧を受けてきた。私は、文学テキストにまつわるイメージや歴史の負荷の研究を、カリカチュアの分析と照らし合わせ、言葉とは別の媒体を用いる造形芸術や音楽等の分野においても、原理的には同じく存在する精神世界の部分に関わっていきたい。
芸術は、現状批判という混じりけのない言語を話すゆえに、独裁権力からは常に真っ先に攻撃・統制・抑圧を受けてきた。私は、文学テキストにまつわるイメージや歴史の負荷の研究を、カリカチュアの分析と照らし合わせ、言葉とは別の媒体を用いる造形芸術や音楽等の分野においても、原理的には同じく存在する精神世界の部分に関わっていきたい。