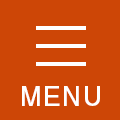教員情報詳細
- 氏名
- 栗田 和典(KURITA Kazunori)
- 所属・職名
- 国際関係学部国際言語文化学科 教授
国際関係学研究科 教授(兼務)
国際関係学研究科附属広域ヨーロッパ研究センター長
- Eメールアドレス
- kurita@u-shizuoka-ken.ac.jp
- ホームページアドレス(URL)
- http://www.kkurita.com/
学歴
1986年3月 名古屋大学文学部史学科西洋史学専攻卒業
1992年3月 名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期課程史学地理学専攻単位取得満期退学
1992年3月 名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期課程史学地理学専攻単位取得満期退学
学位
文学修士(名古屋大学・1988年)
専門分野
西洋史学(18世紀イギリス史)
担当科目
【学部】比較文化入門Ⅰ、国際言語文化入門Ⅲ、英語で読む国際関係入門A、比較文化へのアプローチ(オムニバス)、英米文化論A・B、英米文化特殊研究、演習ⅠA・B、演習ⅡA・B
【全学共通】歴史学入門
【大学院】英米文化研究方法論A・B、イギリス社会史研究A・B
【全学共通】歴史学入門
【大学院】英米文化研究方法論A・B、イギリス社会史研究A・B
主要研究テーマ
- ブリテン史のなかの民衆文化:労働民衆のライフサイクル
- 犯罪の社会史:犯罪的行為、警察、裁判、処刑、都市インフラとしての監獄、恩赦嘆願状
- 公共圏・公共性をめぐる研究:犯罪および裁判の報道
- 植民地経験:北アメリカ植民地ジョージア信託統治団と重商主義的博愛主義
所属学会
・国内
史学会
日本西洋史学会
名古屋近代イギリス研究会
近世イギリス史研究会
・国外
Past and Present Society(UK)
North American Conference on British Studies(USA)
史学会
日本西洋史学会
名古屋近代イギリス研究会
近世イギリス史研究会
・国外
Past and Present Society(UK)
North American Conference on British Studies(USA)
主な経歴
1992年4月 東海学園女子短期大学英文学科専任講師
1995年4月 東海学園大学経営学部専任講師
1997年10月 静岡県立大学国際関係学部専任講師
静岡県立大学大学院国際関係学研究科専任講師(兼担)
1999年4月 静岡県立大学国際関係学部助教授
静岡県立大学大学院国際関係学研究科助教授(兼担)
2007年4月 静岡県立大学国際関係学部教授
静岡県立大学大学院国際関係学研究科教授(兼担)
1995年4月 東海学園大学経営学部専任講師
1997年10月 静岡県立大学国際関係学部専任講師
静岡県立大学大学院国際関係学研究科専任講師(兼担)
1999年4月 静岡県立大学国際関係学部助教授
静岡県立大学大学院国際関係学研究科助教授(兼担)
2007年4月 静岡県立大学国際関係学部教授
静岡県立大学大学院国際関係学研究科教授(兼担)
主な社会活動
教育・研究に対する考え方
歴史を勉強することは精巧なタイムマシンをつくることだともいわれます。過去をひとつの意味のまとまりをもった社会としてながめることで、現代とはちがう社会がたしかにあったことを知り、過去が変化したように、現代もかわる可能性、あるいは複数の選択肢があることを想像できたら、と思います。
I want to be a historian of hope(Natalie Zemon Davis in Visions of History, 1983).
I want to be a historian of hope(Natalie Zemon Davis in Visions of History, 1983).