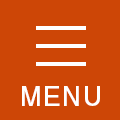教員情報詳細

- 氏名
- 柯 隆(Ke Long)
- 出生年月
- 1963年10月
- 所属・職名
- グローバル地域センター 特任教授
- 電話番号
- 054-245-5600
- 部屋番号
- グローバル地域センター(もくせい会館内)
- Eメールアドレス
- kelong@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
1992年3月 愛知大学法経学部卒業(経済学士)
1994年3月 名古屋大学大学院経済学研究科修了
1994年3月 名古屋大学大学院経済学研究科修了
学位
経済学修士
専門分野
中国経済論、開発金融論
担当科目
グローバル政治経済事情
主要研究テーマ
- 中国経済のサステナビリテイと環境公害問題
- 中国不良債権問題
- 中国のマクロ経済動向
- 中国における国家と市場の関係
主な経歴
1994年 長銀総合研究所国際調査部研究員
1998年 株式会社富士通総研経済研究所主任研究員
1999年~2005年 浙江大学客員教授
2001年~2005年 慶応大学グローバルセキュリティ研究所客員研究員
2006年~2018年3月 株式会社富士通総研経済研究所主席研究員
2012年~ 広島経済大学客員教授
2012年10月~ 静岡県立大学グローバル地域センター特任教授
2018年4月~ 東京財団政策研究所主席研究員、株式会社富士通総研経済研究所客員研究員
1998年 株式会社富士通総研経済研究所主任研究員
1999年~2005年 浙江大学客員教授
2001年~2005年 慶応大学グローバルセキュリティ研究所客員研究員
2006年~2018年3月 株式会社富士通総研経済研究所主席研究員
2012年~ 広島経済大学客員教授
2012年10月~ 静岡県立大学グローバル地域センター特任教授
2018年4月~ 東京財団政策研究所主席研究員、株式会社富士通総研経済研究所客員研究員
受賞歴
2018年 第13回「樫山純三賞」受賞
主な社会活動
財務省外国為替審議会委員歴任(1998年~2011年)
財務省財務総合政策研究所中国研究会委員(1998年~2016年)
JETRO アジア経済研究所業績評価委員 (2003年~2005年)
一般財団法人国際経済交流財団「Japan spotlight」編集委員(2011年~)
財務省財務総合政策研究所中国研究会委員(1998年~2016年)
JETRO アジア経済研究所業績評価委員 (2003年~2005年)
一般財団法人国際経済交流財団「Japan spotlight」編集委員(2011年~)
教育・研究に対する考え方
日本を再生させるために、教育を強化しないといけない。
研究は知識を創造するためのプロセスであり、政治に対する建設的な提言のために、より高度な研究が求められている。
研究は知識を創造するためのプロセスであり、政治に対する建設的な提言のために、より高度な研究が求められている。