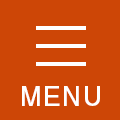教員情報詳細
- 氏名
- 橋川 裕之(HASHIKAWA Hiroyuki)
- 出生年月
- 1974年7月
- 所属・職名
- 国際関係学部国際言語文化学科 准教授
国際関係学研究科 准教授(兼務)
- 部屋番号
- 一般教育棟2602号室
- Eメールアドレス
- hashikawa@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
1997年3月 京都大学文学部史学科(西洋史学専攻)卒業
1999年3月 京都大学大学院文学研究科修士課程(歴史文化学専攻西洋史学専修)修了
2004年12月 バーミンガム大学ビザンティン・オスマン・近代ギリシャ研究所修士課程(M.Phil. in Byzantine Studies)修了
2007年3月 京都大学大学院文学研究科博士後期課程(歴史文化学専攻西洋史学専修)修了
1999年3月 京都大学大学院文学研究科修士課程(歴史文化学専攻西洋史学専修)修了
2004年12月 バーミンガム大学ビザンティン・オスマン・近代ギリシャ研究所修士課程(M.Phil. in Byzantine Studies)修了
2007年3月 京都大学大学院文学研究科博士後期課程(歴史文化学専攻西洋史学専修)修了
学位
文学士(京都大学・1997年)
文学修士(京都大学・1999年)
哲学修士(バーミンガム大学・2004年)
文学博士(京都大学・2007年)
文学修士(京都大学・1999年)
哲学修士(バーミンガム大学・2004年)
文学博士(京都大学・2007年)
専門分野
西洋中世史、ビザンティン帝国史、ギリシャ文化史
担当科目
ヨーロッパ史Ⅰ A・B、ヨーロッパ文化総論A・B、西洋古典語学Ⅰ A・B (ギリシャ語)、原典講読V ②A・B、演習Ⅰ A・B、演習Ⅱ A・B、卒業研究、ヨーロッパ文化入門A(オムニバス講義)、ヨーロッパ文化研究Ⅱ(大学院)
主要研究テーマ
- ビザンティン帝国における教会・修道院改革の展開
- 中世におけるキリスト教神秘主義の系譜
- 東西キリスト教世界の発展と交流
- 古代ギリシャの文学、哲学、歴史記述
所属学会
史学研究会(編集委員、2003年-07年)
日本西洋史学会
日本オリエント学会
The Society for the Promotion of Byzantine Studies
法制史学会
日本宗教学会
日本西洋史学会
日本オリエント学会
The Society for the Promotion of Byzantine Studies
法制史学会
日本宗教学会
主な経歴
1998年4月~2001年3月 京都教育大学附属高等学校非常勤講師
2002年11月~2003年3月 21世紀COEプログラム教務補佐員(京都大学大学院文学研究科)
2003年4月~2005年3月 日本学術振興会特別研究員(DC2)
2005年4月~2007年9月 日本学術振興会特別研究員(PD)
2005年4月~2007年9月 三重大学非常勤講師
2007年4月~2007年9月 大阪教育大学非常勤講師
2007年4月~2007年9月 兵庫教育大学非常勤講師
2007年10月~2009年3月 早稲田大学高等研究所助教
2008年4月~2009年3月 早稲田大学第一文学部(講義)、国際教養学部(講義とセミナー)、オープン教育センター(後期、オムニバス講義)兼担講師
2009年4月~ 現職
2009年6月~ 早稲田大学ヨーロッパ文明史研究所招聘研究員
2010年9月~2015年3月 東海大学短期大学部 非常勤講師
2012年9月~2013年3月 立教大学文学部 兼任講師
2002年11月~2003年3月 21世紀COEプログラム教務補佐員(京都大学大学院文学研究科)
2003年4月~2005年3月 日本学術振興会特別研究員(DC2)
2005年4月~2007年9月 日本学術振興会特別研究員(PD)
2005年4月~2007年9月 三重大学非常勤講師
2007年4月~2007年9月 大阪教育大学非常勤講師
2007年4月~2007年9月 兵庫教育大学非常勤講師
2007年10月~2009年3月 早稲田大学高等研究所助教
2008年4月~2009年3月 早稲田大学第一文学部(講義)、国際教養学部(講義とセミナー)、オープン教育センター(後期、オムニバス講義)兼担講師
2009年4月~ 現職
2009年6月~ 早稲田大学ヨーロッパ文明史研究所招聘研究員
2010年9月~2015年3月 東海大学短期大学部 非常勤講師
2012年9月~2013年3月 立教大学文学部 兼任講師
主な社会活動
教育・研究に対する考え方
「教育及び研究に対する考え方を簡潔に記入せよ」という要請に対し、私が最初に感じたのは戸惑いです。あらゆる局面において可能な限り誠実かつ率直であるよう努めつつ、好きなことを学び、好きなことを教えるのが、私の基本的なスタンスといえるでしょうが、これが適切な応答であるのか否か自信がありません。自伝的な話を長々としたい欲求に駆られますが、ここではそうする代わりに、私が最近読んで強い共感を覚えた、二人の学者の文章を引用します。
「学問とは常に暴露の試みであるべきであり、事実の暴露、それも往々にして「不快な事実」の暴露であるべきなのである。(中略)学問的営為とは研究者にとっては、これまで自分を支えてくれた甘美な幻想をおのれの手で破壊してゆく作業のことなのであり、そして自分の幻想が次々と破壊されてゆくというこの心理的に過酷なプロセスに極限まで耐え続け、にもかかわらず理想を捨てぬことなのである」(羽入辰郎『マックス・ヴェーバーの犯罪─『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊─』、ミネルヴァ書房、2002年、6頁)
「考えをまとめたり、仕事をしたり、書きものをしていて、公共空間、公共の場にあえて何かしらの「真実」を示したいと思ったときには、この世界にあるどんな力であろうと、私の邪魔だてをすることはできません。これは勇気があるとかないとかの話ではありません。たとえいまだ世に入れられてはいないとしても、「真」なる仕方で何かを発言したり思索せねばならぬと考えるときは、世界中のどんな権能であれ私の意思をくじくことはできないのです」(ジャック・デリダ、逸見龍生訳「傷つける真理──言語の格闘」、『現代思想』(緊急特集ジャック・デリダ)、2004年12月号、69-70頁)
追記 この教員プロフィールを目にしてしまった本学学生に薦める10冊の書物。
○古典・小説
1. プラトン『饗宴』(久保勉訳、岩波文庫、1965年;朴一功訳『饗宴/パイドン』、京都大学学術出版会、2007年など)
2. アウグスティヌス『告白』(服部英次郎訳、岩波文庫、1976年など)
3. 夏目漱石『道草』(『漱石全集』10巻、岩波書店、1994年)
4. 同『明暗』(『漱石全集』11巻、岩波書店1994年)
5. 水村美苗『私小説from left to right』(新潮社、1995年;新潮文庫、1998年;ちくま文庫、2009年)
○その他
6. 小坂晋『漱石の愛と文学』(講談社、1974年)
7. 小谷野敦『恋愛の超克』(角川書店、2000年)
8. 佐々木英昭『「新しい女」の到来─平塚らいてうと漱石─』(名古屋大学出版会、1994年)
9. 羽入辰郎『学問とは何か─『マックス・ヴェーバーの犯罪』その後─』(ミネルヴァ書房、2008年)
10. 『音楽と人』179号(2009年4月号)
(2009年3月17、18日 執筆)
「学問とは常に暴露の試みであるべきであり、事実の暴露、それも往々にして「不快な事実」の暴露であるべきなのである。(中略)学問的営為とは研究者にとっては、これまで自分を支えてくれた甘美な幻想をおのれの手で破壊してゆく作業のことなのであり、そして自分の幻想が次々と破壊されてゆくというこの心理的に過酷なプロセスに極限まで耐え続け、にもかかわらず理想を捨てぬことなのである」(羽入辰郎『マックス・ヴェーバーの犯罪─『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊─』、ミネルヴァ書房、2002年、6頁)
「考えをまとめたり、仕事をしたり、書きものをしていて、公共空間、公共の場にあえて何かしらの「真実」を示したいと思ったときには、この世界にあるどんな力であろうと、私の邪魔だてをすることはできません。これは勇気があるとかないとかの話ではありません。たとえいまだ世に入れられてはいないとしても、「真」なる仕方で何かを発言したり思索せねばならぬと考えるときは、世界中のどんな権能であれ私の意思をくじくことはできないのです」(ジャック・デリダ、逸見龍生訳「傷つける真理──言語の格闘」、『現代思想』(緊急特集ジャック・デリダ)、2004年12月号、69-70頁)
追記 この教員プロフィールを目にしてしまった本学学生に薦める10冊の書物。
○古典・小説
1. プラトン『饗宴』(久保勉訳、岩波文庫、1965年;朴一功訳『饗宴/パイドン』、京都大学学術出版会、2007年など)
2. アウグスティヌス『告白』(服部英次郎訳、岩波文庫、1976年など)
3. 夏目漱石『道草』(『漱石全集』10巻、岩波書店、1994年)
4. 同『明暗』(『漱石全集』11巻、岩波書店1994年)
5. 水村美苗『私小説from left to right』(新潮社、1995年;新潮文庫、1998年;ちくま文庫、2009年)
○その他
6. 小坂晋『漱石の愛と文学』(講談社、1974年)
7. 小谷野敦『恋愛の超克』(角川書店、2000年)
8. 佐々木英昭『「新しい女」の到来─平塚らいてうと漱石─』(名古屋大学出版会、1994年)
9. 羽入辰郎『学問とは何か─『マックス・ヴェーバーの犯罪』その後─』(ミネルヴァ書房、2008年)
10. 『音楽と人』179号(2009年4月号)
(2009年3月17、18日 執筆)
研究シーズ集に関するキーワード
古代ギリシャ・ローマ文明、ビザンティン帝国、ヘレニズム、キリスト教、哲学、歴史叙述