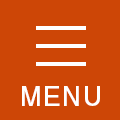教員情報詳細
- 氏名
- 太田 尚子(OTA Naoko)
- 所属・職名
- 看護学研究科(助産学) 教授
看護学部看護学科(母性看護学) 教授(兼務)
- 部屋番号
- 看護学部棟(小鹿キャンパス)14410号室
- Eメールアドレス
- n-ota@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
1984年3月 筑波大学医療技術短期大学部看護学科 卒業
1985年3月 京都大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻 修了
1995年3月 東京大学医学部保健学科 卒業
2004年3月 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程 修了
2009年3月 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士後期課程 修了
1985年3月 京都大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻 修了
1995年3月 東京大学医学部保健学科 卒業
2004年3月 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程 修了
2009年3月 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士後期課程 修了
学位
看護学博士(聖路加看護大学・2009年)
専門分野
母性看護学・助産学
担当科目
【学部】母性看護援助論Ⅰ、卒業研究B
【大学院】母子相互作用支援論、実践看護学特論Ⅴ、実践看護学応用演習Ⅴ、実践看護学特別研究、看護学研究特講
助産学特論、助産学応用演習、妊娠期助産診断技術学、統合ヘルスケア論、妊娠期助産診断技術学演習、助産学基礎演習、地域助産学実習、助産学課題研究、助産学概論、母子保健包括支援論、周産期学、リプロダクティブ・ヘルス演習、周産期助産学演習、助産診断学演習、助産技術学演習、助産学実習、助産学統合実習
【大学院】母子相互作用支援論、実践看護学特論Ⅴ、実践看護学応用演習Ⅴ、実践看護学特別研究、看護学研究特講
助産学特論、助産学応用演習、妊娠期助産診断技術学、統合ヘルスケア論、妊娠期助産診断技術学演習、助産学基礎演習、地域助産学実習、助産学課題研究、助産学概論、母子保健包括支援論、周産期学、リプロダクティブ・ヘルス演習、周産期助産学演習、助産診断学演習、助産技術学演習、助産学実習、助産学統合実習
主要研究テーマ
- 周産期の死別(ペリネイタル・ロス)のケアに関する研究
- ペリネイタル・ロスのセルフヘルプ・グループに関する研究
- インストラクショナル・デザインによる看護教育プログラムの開発と評価
所属学会
日本助産学会
日本看護科学学会
日本臨床死生学会
聖路加看護学会
日本母性衛生学会
日本助産学会(専任査読委員、代議員)
日本グリーフ・ビリーブメント学会
日本混合研究法学会
静岡県母性衛生学会(理事)
日本看護科学学会
日本臨床死生学会
聖路加看護学会
日本母性衛生学会
日本助産学会(専任査読委員、代議員)
日本グリーフ・ビリーブメント学会
日本混合研究法学会
静岡県母性衛生学会(理事)
主な経歴
・筑波大学附属病院(助産師)
・茨城県立医療大学 助手(母性看護・助産学)
その他、厚生労働省医政局看護課看護専門調査員、女子栄養大学 非常勤講師、山梨大学非常勤講師、聖路加看護大学看護実践開発研究センター客員研究員、静岡県立大学非常勤講師 など
・茨城県立医療大学 助手(母性看護・助産学)
その他、厚生労働省医政局看護課看護専門調査員、女子栄養大学 非常勤講師、山梨大学非常勤講師、聖路加看護大学看護実践開発研究センター客員研究員、静岡県立大学非常勤講師 など
受賞歴
2006年 日本助産学会20周年記念論文優秀賞
2010年 日本助産学会学術集会 優秀ポスター賞
2010年 日本助産学会学術集会 優秀ポスター賞
主な社会活動
聖路加国際大学研究センター「天使の保護者ルカの会」 スタッフ
日本ペリネイタル・ロス研究会 代表
日本ペリネイタル・ロス研究会 代表
教育・研究に対する考え方
教育:科学的根拠に基づくケアと人間的なケア、自然な出産と医療介入が必要なハイリスクの出産、実践と研究の統合、女性たちとのパートナーシップなど、バランスのとれたケアや研究ができる看護師や助産師を育てたい。
研究:女性中心のケアを提供するための、女性たちとの協働による、臨床に根ざした研究。
研究:女性中心のケアを提供するための、女性たちとの協働による、臨床に根ざした研究。
研究シーズ集に関するキーワード
ペリネイタル・ロス,死産,新生児死亡,死別,グリーフケア,セルフヘルプ・グループ,助産教育,教育プログラム,インストラクショナルデザイン