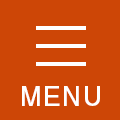教員情報詳細
- 氏名
- 鈴木 さやか(SUZUKI Sayaka)
- 所属・職名
- 国際関係学部国際言語文化学科 教授
国際関係学研究科 教授(兼務)
- Eメールアドレス
- iwakura@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
2006年 九州大学大学院人文科学府卒業
学位
博士(文学)(九州大学・2006年)
専門分野
日本古典文学
担当科目
原典購読Ⅲ2A・B、日本文学研究ⅠA・B、日本文学史A・B
主要研究テーマ
- 世阿弥による能楽論及び世阿弥作の謡曲(中世)
- 各務支考による俳論及び蕉門俳諧(近世)
所属学会
能楽学会
絵本学会
九州大学国語学国文学会
絵本学会
九州大学国語学国文学会
主な経歴
2006年4月 日本学術振興会特別研究員(PD)採用
2006年10月 静岡県立大学国際関係学部 講師 就職
2006年10月 静岡県立大学国際関係学部 講師 就職
主な社会活動
学生有志による能「羽衣」普及活動団体「羽衣つたえ隊」主催
教育・研究に対する考え方
・教育
学生が、古人の含蓄ある言葉を多く取り入れることで、思考の幅を広げ、心のひだを増やすことができるよう、手助けする。自分たちが使っている言葉の背景には、千数百年にわたる先人たちの文学的営みがあるのだということを意識させる。向かい合うよりも、同じ方向を見つめる同行(どうぎょう)でありたい。
・研究
学ぶはまねぶ。古人の言葉によって自己が変容したとき、はじめて「知る」という行為は成り立つのだと考える。詳細な考証を重ねつつも、単なる作品の分解に終わらず、作者が言葉を発したそもそものきっかけ・源泉に常に立ち返るよう心がけたい。
学生が、古人の含蓄ある言葉を多く取り入れることで、思考の幅を広げ、心のひだを増やすことができるよう、手助けする。自分たちが使っている言葉の背景には、千数百年にわたる先人たちの文学的営みがあるのだということを意識させる。向かい合うよりも、同じ方向を見つめる同行(どうぎょう)でありたい。
・研究
学ぶはまねぶ。古人の言葉によって自己が変容したとき、はじめて「知る」という行為は成り立つのだと考える。詳細な考証を重ねつつも、単なる作品の分解に終わらず、作者が言葉を発したそもそものきっかけ・源泉に常に立ち返るよう心がけたい。
研究シーズ集に関するキーワード
能「羽衣」、地域の「物語」の活用、学生による地域貢献、「羽衣」絵本