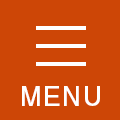教員情報詳細
- 氏名
- ファイファー マティアス(PFEIFER Matthias)
- 所属・職名
- 国際関係学部国際言語文化学科 准教授
国際関係学研究科 准教授(兼務)
- Eメールアドレス
- pfeifer39@u-shizuoka-ken.ac.jp
学歴
1993年2月 Goethe-Universität Frankfurt, Fb Neuere Philologien - Germanistk(ゲーテ大学、フランクフルト、現代文学語学学部、ドイツ文学学科卒業)
学位
文学修士(M.A.,Goethe-Universität Frankfurt・1993年)
専門分野
文化社会学(映像、文学、音楽)
担当科目
ドイツ語入門、ドイツ語Ⅰ、ドイツ語Ⅳ、演習Ⅰ・Ⅱ、Introduction to Modern Japanese Culture(現代日本文化入門)、映像と社会、ドイツ文化論
主要研究テーマ
- 自叙伝文学
- 移民文化
- アイデンティティ論
- 現代社会と戦争
所属学会
ドイツ学会
主な経歴
1994年4月 静岡県立大学教養部専任講師
1995年4月 静岡県立大学国際関係学部専任講師
2011年9月 静岡県立大学国際関係学部准教授
1995年4月 静岡県立大学国際関係学部専任講師
2011年9月 静岡県立大学国際関係学部准教授
主な社会活動
ドイツ語市民講座講師(静岡日独協会)
教育・研究に対する考え方
「他文化を知らない者は、自国の文化もよく理解できない」とはゲーテ詩人の名言である。つまり、外国の文化を知ることによって初めて、当たり前のように思っている自国の習慣、ものの扱いや考え方を違う視点から評価できる。ものごとから距離をおき、客観的な判断を行うことが研究者の仕事であり、大学生の課題でもある。しかしまた、「自分の文化を知らなければ外国の文化も理解できない」とも言える。日本の文化を無視して外国の文化だけにこだわる者は、結局比較する文化を持たない人間であり、新しいものの良し悪しを判断できない。「それでは、どう勉強を始めればいいのか?」と、迷ってしまった新入生は聞いてくれるだろう。まず、自分の文化から始めるのか、それとも外国の文化からアプローチする。
研究シーズ集に関するキーワード
戦争責任、文化とアイデンティティ、集合的記憶、日本人論